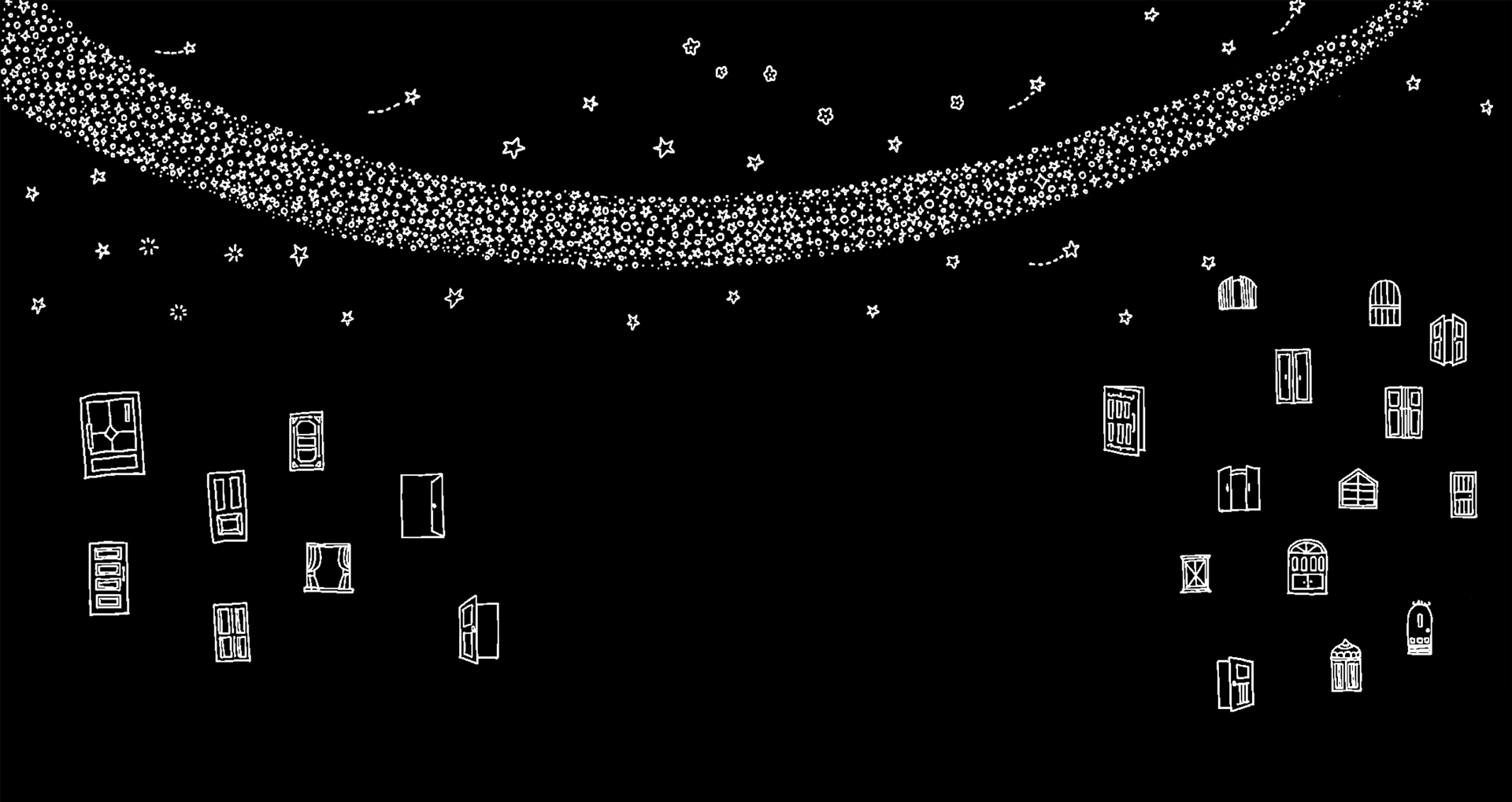先日、学生時代の友人に会いました。
仲の良い友人というものは、どんなに時間が空いて「久しぶり!」なんて挨拶を交わしても、なんだかあまり「懐かしい」という気がしないものです。
「久しぶり!(なんだか先週も会った気がするけど…)」なんて心の中で思いながら、でもお互いなんだか変わったところはあるかな?自分の知らない人になっていないだろうか?などと探りながら、ふわふわと話しはじめます。
話はお互いの近況報告からはじまり、「あのころこんなことがあったね。」と思い出話に移ります。
「こんなことがあったね。」
「あんな場所に行ったね。」
「あの人は本当に愉快だったね。」
「またいつかあそこに行ってみたいね。」
それはとてもうれしくて、すこし淋しい時間です。きっと、学生時代に一緒にいたころは、近況報告はもちろん、思い出話なんてする必要がなかったでしょう。
思えば、最近は友人に会うと近況報告と思い出話ばかりな気がします。それぞれの日常は学生時代より交わることが少なく、昔からの友人との語らいは小さな非日常です。その中で僕たちは、僕たちしか知らない街の話をします。
僕たちの学生時代の日常だったいくつかのお店 - 駅前の甘味処や雀荘キャベツ、『すすき』と
もはや、僕が僕たちの学生時代の居場所をたどるには、思い出に頼るしか方法
なるほど「思い出」というのはとてもやっかいなもので、
僕たちをいとも簡単に、「あのころはよかったな」とぼやくオジサンにしてしまう。「あのころはよかったな。いまはいろいろと生きにくいよ。」という彼ら(僕ら)は、きっと「尊敬すべき頼れる大人」の顔をしていません。
けれど、共有している「思い出」をこっそりと見せ合うとき、僕たちは誰よりも幸せな「あのころの僕たち」でもあります。
それはまさに、寺山修司の『幸福論』をなぞれば、
思い出ということばは、科学を裏切る。人は思い出を持つことができるが、事物は思
い出を持つことが出来ないからである。
思い出は、個人的な蓄積であるが、ときには疎外された人間たちの失地回復の<緑の土地>になることもあり得る
からなのでしょう。
1日中たっぷりと話をしたあと、
「こんどは思い出話じゃなくて、もっとくだらない話だらけにしたいね。」
そういって、彼女はいまの彼女の居場所に帰っていきました。
そんな日も、いつか未来のよい思い出です。